![]()
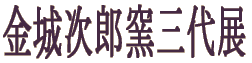
 線彫花文大抱瓶 |
金城次郎1912年 那覇市生まれ 1924年 壺屋で陶器を習う 1946年 那覇市壺屋に窯場を開く 1956年 国展新人賞 1969年 日本民藝館賞 1972年 読谷村座喜味に窯を移す 1977年 現代の名工 1981年 勲六等瑞宝章 1985年 人間国宝認定 |
 魚文湯呑 三彩点文湯呑 |
 黍文香盒 魚文香盒 |
 黍文注子 |
 唐草文鉢 |
 三彩点文蓋物 |
 幾可文水滴 魚文水滴 |
 蟹文壷 |
金城敏男1936年 那覇市生まれ 1957年 国展初入選 1977年 銀座松屋で親子展 1982年 沖展会員 1986年 沖縄県優秀技能賞 1992年 沖縄タイムス芸術選大賞 2001年 伝統的工芸品振興功労者 2004、06、09年 銀座たくみで金城窯三代展 |
 竹文台皿 |
 海老魚文嘉瓶 |
金城吉彦1967年 那覇市生まれ 1990年 父(敏男)の元で焼物学ぶ 1998年 現代沖縄陶芸展初入選 1999年 妻・博美と金城陶器所始める 2002年 宜野湾市ギャラリーで四人展 2004年 銀座たくみで金城窯三代展 2006年 沖展奨励賞 2006、09年 銀座たくみで金城窯三代展 |
 象嵌土瓶揃 |
 海老文ジョッキ |
 三島皿 白磁透彫胡瓜文筆筒 |
金城博美1966年 愛媛県今治市生まれ 1994年 焼物を始める 1998年 今治市河野美術館で四人展 1999年 夫・吉彦と金城陶器所始める 2002年 宜野湾市ギャラリーで四人展 2004年 銀座たくみで金城窯三代展 2006年 沖展入選 2006、09年年 銀座たくみで金城窯三代展 2009年 沖展奨励賞 |
 蟹文ぐい呑 魚文ぐい呑 蟹文渡名喜瓶 |
その後太平洋戦争で沖縄島民の半分以上が死傷したという惨禍の中で、しかし壺屋は奇蹟的に登り窯が二つ残りました。21年1月、沖縄の復興とともに、金城次郎さんも新垣栄徳の窯のそばに自らの仕事場を持ち独立します。そしてマカイ(飯碗)やワンブー(丼)、皿、徳利、厨子がめをはじめ求められるあらゆる器を作り続けました。
沖縄らしさを失うことなく、しかし誰の真似でもない独自の作風を心がけた次郎さんの作品は、濱田先生の強い支えもあって次第に人気を呼び、本土復帰前の昭和46年、東京のたくみで第一回の作陶展を開催します。
この会は、金城次郎という一陶工の作品を東京の目利きに認知してもらおうという、濱田の強い希望によって企画され、出品作品はすべて次郎の窯で濱田自ら選んだものばかりでした。
そのころ私は次郎さんの作による百数十に及ぶ水滴の数々を見たことがあります。十数種に及ぶ形の多様さと、草文、くし描き、象嵌、いっちん、二彩、点文、ハート文など興に応じて描かれる多彩な模様は次郎さんならではのものでした。そして次郎さんは、昭和60年3月、国の重要無形文化財指定、いわゆる人間国宝に認定されました。
今、そのあとを継いで長男の敏男さん、さらに孫にあたる現当主の吉彦さん、博美さんのご夫婦が読谷壺屋の金城窯で、それぞれの作風を生み出しながら作陶に励んでいます。金城窯の特色である魚文も、次郎,敏男、吉彦さんのそれぞれに特徴があります。
そして金城窯の皆さんが、登り窯を守り、なんとも言えない壺屋の陶器の肌の美しさを愛しながら、次郎さんがそうであったように、自由な感覚で新しい創作に挑まれることも期待しています。
志賀直邦