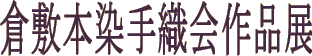倉敷本染手織研究所の仕事
所長 石上信房
倉敷本染手織研究所は昭和28年春に発足しました。生活の隅々に民藝品をいきわたらせるという民藝運動の大目標の実現の為に研究所を開いた外村吉之介には織物の工人養成の経験がありました。
最初の弟子は、第二次世界大戦の前、静岡県袋井のキリスト教会で外村が牧師をしていた時、伝道の一環として織物を教えていた女性達でした。外村は「信仰と工藝は一如」の信念を貫きました。この時の弟子の一人は、数年前に引退するまで織物を続けておられました。
二番目の工人は、第二次大戦中倉敷紡績の工場で日本軍の軍需物資を作るために動員されて来た沖縄の女性達でした。戦争が終わったもののすべてが破壊された沖縄には帰るあてもありませんでした。その女性達に織物の教育をしようとの大原社長の配慮と柳宗悦先生の推薦で、外村が取り組むことになりました。沖縄の女性達は21年秋に帰路に付かれ、この時の弟子の一人平良敏子さんは沖縄の喜如嘉で今も芭蕉布と取り組んでおられ、その業績が認められて人間国宝になられました。
三番目は、第二次大戦の直後、倉敷に駐屯していたイギリス軍の兵士達でした。当時貧しかったインドやネパール出身の兵士に対する退役後の生活手段のための職業訓練で、織物の教習を兵営の中で行いました。昭和25年に朝鮮戦争が始まると職業訓練どころではなくなり、兵士達は戦争に駈りだされていきました。
四番目は、外村宅で随時入所・随時卒業の形で研究所の発足までいた人達です。
そして、昭和28年の研究所の発足から平成5年の外村の逝去までの40年間に卒業したのは211人にのぼります。修業期間は1年間、弟子は常時5〜7人で、外村夫妻と起居を共にするいわゆる内弟子が過半数でした。逝去の1年後の平成6年に再開して、今年の春までに卒業した弟子の総数は400人を超えました。
私生活を共にすることは教育内容が染織の技術だけでなく生活全般におよぶことを意味しました。発足後しばらくの間は、高校を卒業して間もない感受性豊な若い弟子が多く、それ故に生涯にわたる極めて大きなことを学びました。それはジャムの作り方や雑巾がけ等の生活技術から、民藝美論を骨にした暮らしのあり方、物の見方、人生のあり方まで広い範囲に及びました。
日常に使う品は民藝品ばかりで、いつも「いいね、いいね」と喜んで使いました。弟子は「日々美の喜び」を目前に観たのでした。
それが九州の小鹿田窯や山陰の出西窯の焼物だと言っては「京 遠く美近し」を無言の内に教わりました。
民藝品の美を讃えるものの、桐箱に収めて生活に活かさない様を「玩物喪志」と言って強く戒めました。
有名作家になることを目標とせず、家族の生活、地域の暮しを清める工人になってほしいとの心を「無名本然」と表して食堂の壁に掲げました。
織物の材料は木綿が主でした。木綿は暖かく、汗を吸い、体の汚れを取り、洗濯ができる、安くて健康によい最高の繊維だからです。そしてさらに、決して華やかな「よそ行き」になることはなく、日常を支える普段着となり、赤子のおしめになり、最後は身辺の汚れを清める雑巾になってその生涯を閉じる様を「木綿往生」と讃えて、人の生き方の目標にしました。「往生」とは「極楽浄土に生まれかわる」の意であります。
師弟関係は家庭的な雰囲気を旨としましたが、修行の場として厳しくもありました。修業は全員に一様に厳しいが、卒業後に作る品にそれぞれの人柄が表われる様を「風雪一丹青萬」(ふうせつひとつ、たんせいよろず)と言って喜びました。「寒い冬が過ぎて春が来ると山野は赤や緑に満ちる」の意であります。
外村の逝去から26年を経た現在も、「研究所で得た最大の財産は、染織の技術ではなく、人生のあり方そのものだった」と弟子達の多くが告白されています。
「信仰と工藝は一如」だったのであります。
|
![]()